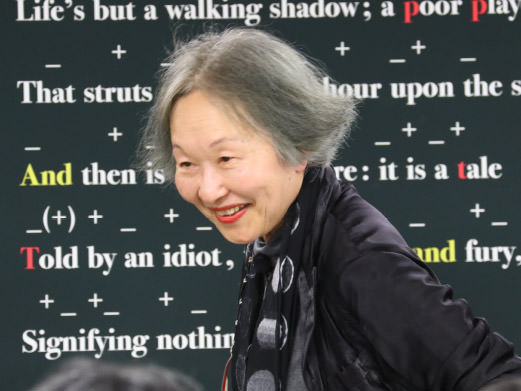[第3回]深く呼吸するために。
-

河野 - 改めて尋ねたいんですが、
浪曲の発生とか、歴史というのはどういうものなんですか?
-

奈々福 - もともと「浪花節」というジャンルが生まれたのは
明治の初期なんです。
ただ、明治の初期にいきなりできたわけじゃなくて
すごーくざっくりした
わたしの浪曲史観ですけど‥‥。
-

河野 - 浪曲史観?
-

奈々福 - はい。
芸能者って誰でも自分自身の芸能を軸にした
芸能史観を持ってると思うんですよ。
-

河野 - うん。
-

奈々福 - 歴史全然詳しいわけではないんですが、
なんとなく、
鎌倉仏教が日本の語り芸を生んだ
一つのポイントだと思っています。

-

奈々福 - そもそも仏教っていうのは平安時代まで
貴顕(※)の人たちのものだったんですよね。
でも、貴顕の支えを失い、武家に政権が移った時、
寺社仏閣ともども
生き残るにはどうしようかと考えたと思うんです。
※きけん:身分が高く、名声があること。
鎌倉仏教が数々興って、
その鎌倉仏教は貴顕の方を向かなかった。
まず民衆の方を向いんたんです。
目に一文字もない人たちに
仏教の教えを伝えるため、
そこに説教、つまり語りのテクニックというのが生まれてきた。
-

河野 - なるほど。
-

奈々福 - あと、声明とか声のテクニックも
その頃に生まれたらしいんです。
そういう声と語りのテクニックが、
勧進僧とか聖とか、
歩き巫女とか瞽女(※)とか、底辺の芸能に流れ込んでいって、
それが説経節とか祭文とか、
幕末の頃にはちょぼくれとかちょんがれとか
阿呆陀羅経とかいろんな大道芸に花咲いた。
それが明治政府になってから、
そういう大道芸が禁止にされちゃったんです。
※ごぜ:三味線を手に村々を流し歩く目の不自由な女性。
-

河野 - うん。
-

奈々福 - で、明治政府の芸人鑑札がないと
芸能活動ができなくなったということがあって
これは困るというので、
いろんなジャンルの節付きの物語を語る人たちが
大同団結して、東京で浪花節の鑑札を得た、
というところから始まった、らしいんです。
それまで担ってた人たちは、
士農工商の外側の人たちだった。
だから明治になっても、差別されて、
なかなか寄席に上げてもらえなくて
葭簀張り(※)の小屋掛でやってた時期が長かったみたいです。
※よしずばり:よしずで囲うこと。
明治20年代からだんだんと
寄席に上がるようになりますが、
落語からも講談からも「あんな奴ら」と
浪曲は下に見られていた。
実際、粗野で下品なところもあったと思うんです。
それが少しずつ、人気も出てきて、
洗練されてきて、
でもまだ差別はあってという明治30年代の後半に
自由民権運動から生まれた、
「演説」というスタイルが人気になって。

-

河野 - はい。
-

奈々福 - あと、明治37年に日露戦争が起こって
勝ったとはいえ、ああいう形で戦争が終わって
「勝ったのに、何、この条件」みたいな。
そうやって国威発揚の機運がすごく高まってた時に
北九州に玄洋社という右翼団体があって‥‥
-

河野 - 頭山滿のですね。
-

奈々福 - そうです。
その玄洋社が浪花節を、
演説のスタイルに落とし込み、
武士道鼓吹を謳いあげる
忠臣蔵みたいなものの台本を整えて、
派手に宣伝した。
そうして、桃中軒雲右衛門という
スターを作ったんですね。
-

河野 - なるほど、そこに繋がるんだ。
-

奈々福 - で、これが当時の世相とマッチして、
大売れしたものですから
全国的に浪花節人気が爆発した。
そこから、山があり谷がありとはいえ、
昭和30年代前半くらいまで、
日本で一番人気のある芸能が浪曲だったんです。
その頃には、
芸でいうと私のひいおじいちゃんにあたる
二代目玉川勝太郎とか、
春日井梅鴬だとか、三門博だとか、
錚々たる浪曲師たちがいたんです。
昭和22年の芸能人長者番付というのが
私の手元にあるんですが
トップ10のうち6人が浪曲師です。
-

河野 - へぇ。
-

奈々福 - 今、空前の落語ブームだと言われて
東西合わせて落語家さんが
900人いるそうなんです。
でも昭和18年には浪曲師は
全国に3000人いたんですよ。
-

河野 - まさにその時は国民的芸能だった。
-

奈々福 - まさにその時は国民的芸能だった。
-

河野 - そこから日本が高度成長の道を
まっしぐらという中で
浪曲がどんどんと退潮していく。

-

奈々福 - はい。
-

河野 - 現在の浪曲師は何人なんですか?
-

奈々福 - 東西合わせて80人です。
-

河野 - そのうち女性は?
-

奈々福 - 女性の方が圧倒的に多いです。
男性は少ないです。
絶滅危惧芸能です、ほんとうに。
でもここ最近、新しい人が入ってきてはいるんです。
-

河野 - じゃあ、絶滅危惧芸能っていうのは、
下がいないというより、上の層が薄いっていう。
-

奈々福 - そうですね。ほんとうに上が薄くなってます。
先輩方が少なくなっちゃいました。
私が入った時は、この浪曲を見よ! って人が
ズラーっといたんですけど、
今は少なくなっちゃった。そこが辛いです。
-

河野 - 奈々福さんが担う役割は大きいと思うんですが
いま浪曲に力を与えるために、
古典とのお付き合いを続けておられるんですよね?
-

奈々福 - はい。
-

河野 - それですぐに浪曲師が増えたり、
お客さんの数が増えたりは
しないかもしれないけど、
目に見えない形できっと奈々福さんの芸に
力を与えてくれるものになっているんだろうと思います。
-

奈々福 - それは確実にあります。
-

河野 - 筑摩の編集者時代に
『源氏物語』とか
古典に関わる仕事をしていたとはいえ、
浪曲師に軸足移してから
改めて古典を勉強しようとしたのは
何がきっかけですか?
-

奈々福 - ひとつは能楽師の安田登先生との出会いが大きいですね。
いま、安田先生の『古事記』の講座に通ってるんです。
お能は650年続いている芸能で、
もともと詞章が、
和歌や平家物語をはじめとして日本の古典文学を
完全に踏まえているものです。
しかも目に見えないものたちとコンタクトする芸能です。
その能楽をやっておられる安田先生の、
『古事記』論。
思考の時間的空間的幅の広さったら、
途轍もないです。
芸能って、いまは目の前のお客さんにアピールするものだけれど、
原初は、鎮魂だったり祈りだったり、
目に見えない世界とつながっていたもの
だったじゃないですか。
でも現代人にその感覚は薄い。
ところが、古代日本人は、
現実と夢を同価値に考え、
見えない世界とも今よりずっとつながっていた。
死に対する感覚もいまとは全然違っていた。
日本人がもともとどういうことを尊んでいたのか
どういう感覚や身体性を持っていたのかを
『古事記』の中から読み取る‥‥
もうびっくりすることが数々あって。
しかも、読むだけではなくて、朗誦してみる。
当時こんなふうに歌われていたのではないか
と考えられる節をつけて、歌ってみる。
1300年前の言葉を詠むって、
なかなかステキですよ。
そのことで立ち上ってくるものがある。

-

河野 - うん。
-

奈々福 - そこにはものすごく自分を自由にしてくれる、
教科書で習ってきた歴史という固い鎖を
解き放ってくれるような
感覚の自由さがあるんです。
-

河野 - うん。
-

奈々福 - それがすごくいまを生きる力になるし、
芸能をやっていく力になると思います。
現代人の身体能力的にいえばありえないでしょ、
ということが
古典文学の中にはあるじゃないですか。
『平家物語』の中の鵯越(ひよどりごえ)とか。
-

河野 - 揺れる船の上の扇の的を射た
「屋島の戦い」の那須与一(なすのよいち)とか。
-

奈々福 - あったんだろうと思うんですよ、あれ。
いまの自分たちの価値基準とか、
身体の基準で考えちゃいけないことで、
あの人たちは見えないものを見る力があったし、
聞こえないものを聞く力があったし、
山を制する民であるか、
馬を御する民であるか、
海の民であるか、
『平家物語』ひとつをとって、
そんな読み方を教わると、
もう、躍動しちゃいますよね。
逆に、『源氏物語』を読むと
「いまと同じじゃん!」みたいなことも
あったりして。
鬱とかマザコンとか引きこもりとか
自分のことをダメだダメだと思い込む男子女子が続々登場して
「うわー、いまに始まった話じゃないんだ」と、
人間の本質は変わらないのだなあと思ったり。
-

河野 - 『古事記』ではどんな講義を受けてるんですか?
-

奈々福 - これがすごーく面白いんですよ。
古事記から探る日本人の古層
ということがテーマで。
-

河野 - 生徒さんの年代は?
-

奈々福 - 幅広いですね。30代から70代まで。
-

河野 - 似たような例としては、
小林秀雄の『本居宣長』を
10年がかりで読もうという私塾があります。
小林秀雄の書籍編集をしていた
新潮社OBを中心に、
有志たちが集まって。
-

奈々福 - わおー、本居宣長。
-

河野 - そうすると結局、
宣長の『古事記伝』に遡っていくんです。
で、やはり目指すところは
日本人の感性の古層を訪ねるということなんです。

-

河野 - 小林秀雄が本居宣長を、
本居宣長が古事記を読みながら
何をもう一回探りあてたいと願ったか、
そういう読み方をしています。
ついには塾生が
自発的に和歌を作り始めたり(笑)。
-

奈々福 - ああ、いいですねー。そうやって学ぶことって、
どこまで想像力の手を伸ばすかというとじゃないかと思います。
私はツイッターを使ってますけど、
すごく目先のことや、断片的な情報ばかりで
呼吸が浅くなるようなことばかりじゃないですか。
-

河野 - うん。
-

奈々福 - 例えば、安田先生はいまシリア語を
勉強していらっしゃるんですが、
それは、イエスが使ったアラム語と、
現在ある言語の中で一番近いのが
シリア語だかららしいんです。
イエスの本当に意図するところ
聖書の古層にも手を伸ばしたいって。
現代を生きている人間が、
どこまで聖書の奥底に手を伸ばしうるのか。
どこまで呼吸を深くできるか、
どこまで想像を深くできるか、
どこまで感覚を伸ばしうるか
っていうことですよね。
古典を読むって、そういうことだと思うんです。
実利があるというよりも、
こんなに呼吸の浅い毎日を生きている中で
どれだけ手を伸ばしうるのかなっていう。
その深さに身を浸して
みんなで学んでいる時間というのは
こんな現代で、稀有なことじゃないですかね。

-

河野 - なるほど。
-

奈々福 - いっぱいできるといいですよね、
こういうローカルな学び舎が。
-

河野 - 奈々福さん自身も
浪曲を通じて古典を広めていくのでしょう?
-

奈々福 - そうですね、
いろんな浪曲の使い方が
あると思うんですけれど‥‥。
寄席というのは唯一油断していい場所なんですよ。
油断できる時間、油断できる空間。
「浪曲って面白いですよ」というより
浪曲というツールを使って、
自分の現実を油断して手放せるような
時間と空間を、
ほんのわずかの間、作れたらいいな
と思っています。
疲れている人たち、傷ついている人たちや、
体を傷めている人たち、そんな人たちの前で、
現実からかけ離れた、
でも、人間の情感あふれる物語を語ることで、
心が緩んで、しばし現実に向き合わなくてもいい時間を作れるのであれば
そういう仕事をしていきたいなと思います。

(おわり)
2018-06-27-WED


![[第3回]「いま、なぜ古典なんだろう?」出版社をやめて浪曲師になりました。](./common/images/page12/page_heading.png)